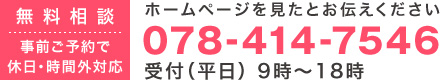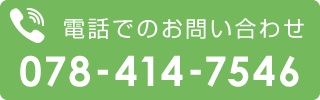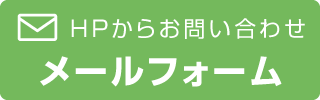Author Archive
登記のオンライン化と裁判のIT化
私たち司法書士の代表的な業務である登記業務。
この登記は、元々書面で法務局に申請する形でしか申請できなかったのはこれまでも何度かお話をしてきました。
書面申請の時代であっても、法務局へ申請を出す、そのものの時間は一瞬です。
しかし、その法務局に行くまでは当然ですが移動時間が必要です。
私は、全ての法務局に行ったわけではありませんが、多くの法務局は、駅から少し離れたところにあり、行くとなるとどうしても時間がかかってしまいます。
例えば、神戸市内で不動産の取引があり、対象の物件は明石という場合。
神戸市内から、明石の法務局までは、30分前後時間がかかります。
法務局が開いているのは、5時15分までということを考えると、4時30分ぐらいまでしか、取引は行うことができません。(実務ではこんなギリギリのことはありませんが。)
しかし、これがオンラインになると、5時10分に取引が終わったとしてもその場で申請が可能です。
このように、手続きのオンライン化は、その場に行く時間、その場から帰る時間を省略できることも大きなメリットです。
さて、この手続きのオンライン化。
司法書士が行う他の業務にも早く導入されてほしいものです。
例えば、裁判所での業務。
司法書士は、認定を受ければ簡易裁判所の代理権を得ることができます。
しかしこの裁判手続き、まだ裁判所への出頭が求められており、中々時間がとられてしまいます。
ただ、この裁判所での手続きも、法務局での登記申請と同じく、出頭してからの時間は一瞬という事件も多くあります。
これも例を挙げると、今は少なくなりましたが、「過払い金返還請求事件」これが代表的な例です。
この過払い金返還請求事件、私たちの業務のほぼ全ての部分を占めるのは、出頭前の書類作成の部分です。
当日は、先方の貸金業者はまず出頭しません。
そうすると、出頭しているのは原告側の私だけです。
当然、話し合うこともなにもありません。
次回の期日を決めるだけで終了です。
時間にして5分未満。
しかしそれでも移動時間は数十分はかかります。
正直、何をやってるんだと思うこともあります。
とはいっても双方欠席はできません。
原告側の私が裁判を止めることはできないので出席するしかないという流れです。
ただ、この辺りもIT化していけば話は変わっていきます。
ZOOMであれば、一瞬の期日でもそれほど苦ではありません。
他にも、裁判所へ提出する書類もオンライン上で申請可能にすれば、どこにいても書類を見て、どこでも書類が作成・提出できるということになります。
多くの役所手続きがオンライン化しているところを見ると、裁判所への手続きでもオンライン化できる部分は多いはずです。
これからそのような流れに転換していくことを期待しながら今日も裁判所へ出頭してきます。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
司法書士と懲戒
司法書士は、業務を行うために司法書士会に入会しております。
私は神戸に事務所を構えているため、兵庫県司法書士会に登録をしており、他にも各都道府県に会が存在しています。
司法書士会では一般の方が会員を検索できるように、名簿も備え付けており、インターネットからでも検索をすることができます。
司法書士会に入っていると毎月、月報司法書士なる書籍が送られてきます。
それには、最新の判例であったり、法改正、豆知識等々様々なものが載っており、ためになる記事も多くあります。
読み物的な記事の中に、「懲戒事例」というものもこの会報には載っています。
割と詳細な事例が載っており、どの部分が悪かったのか、どうすれば良かったのかが読んでわかるようになっています。
司法書士が懲戒になるケースはいくつかありますが、私の体感としては、
・成年後見等での業務上横領(多くは一発業務禁止、若しくは一年以上の業務停止)
・本人確認、意思確認をしなかった(数か月~数年の業務停止が多い)
・事件放置(連絡、理由なく事件に手を付けていない)(数週間~数か月の業務停止が多い印象)
これらがトップというかワースト3によく出てくる懲戒事例です。
これに続くのが、「品位保持義務違反」というものです。
この懲戒事例は、様々な事件から派生し得るものです。
例えば、バックマージンを受け取っていたとか渡していたという例。
司法書士は、お客様や案件を業者などに紹介した場合に、バックマージンを受け取ってはいけません。
相手方で多いのは、不動産業者がほぼ全てを占めます。
不動産業界では、いわゆるバックマージンは特に違法ではないので、私たち司法書士相手であっても同じようにバックマージンを渡したり要求したりという関係になりやすいのです。
ベテランの先生や経験豊富な司法書士であれば、そういった業者とは付き合わなくとも他で十分仕事ができるため、きっぱりと断ることができるのですが、新人の司法書士などはやはり狙われやすいようです。
他には、誇大広告というものもこの品位保持義務違反にあたるようです。
具体的な例は中々難しいですが、「日本一安い司法書士」などの記載はふさわしくないようです。
最初に挙げたような3つのよくある懲戒については、ある意味わざと問題を起こしていますが、品位保持義務違反については、各会員の倫理観が非常に大切です。
懲戒事例を見て、「これで懲戒はかわいそう」とか「これで懲戒は意味が分からない」と感じてしまうということは自分の品位・倫理観がズレているのです。
これからも毎月会報を読みながら司法書士としての倫理観を高めていきたいと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
登記のオンライン申請と「空申請」
現在、多くの司法書士は登記申請をオンラインで行っております。
当然ですが、最初からオンラインの方式があったわけではなく、情報通信技術の発展などが理由で、平成17年ごろからオンライン申請が開始されました。
今となっては、管轄の法務局に申請に行く必要がなくなり、一部の登記を除いては全国各地どこの法務局にも即時に登記申請を行うことができます。
ただ、このオンライン申請、開始されてすぐに今のように普及したわけではありませんでした。
平成17年に制度が開始されてもほぼ利用されることがなかったそうです。
その理由は、公的個人認証の普及率が著しく低かったことが原因です。
具体的には、個人のお客様で「電子証明書」を発行できる人がほとんどいなかったのです。(これは今もそうですが)
平成17年当時、登記のオンライン申請は、個人の登記申請人が電子証明書を発行できることが必須でした。
電子証明書を発行できる個人がいなかった以上、登記のオンライン化も全く進まなかったというのが当時の実情でした。
潮目が変わったのは、平成20年。
オンライン申請に「特例方式」という方式が登場したことでオンライン申請は大きな転換点を迎えました。
特例方式とは、登記申請はオンラインデータで行うものの、添付書類である印鑑証明書・権利証などは郵送や持参などの方式を認めるというものでした。
これにより、電子証明書がなくとも印鑑証明書などの従来の本人確認でもって登記申請が可能となったのです。
これにより、事実上、オンライン申請を行えない登記は数を減らしますが、それでもすぐにオンライン申請が普及したわけではありません。
その理由は様々ですが、その一つに「空(から)申請の防止」があります。
登記は、申請日と申請番号が非常に重要であり、登記を申請した順番により登記順位が決定します。
そこで、オンライン申請を悪用し、実際の取引前に登記申請だけ行い、添付書類は後から追完することが技術的に可能になってしまったのです。
それを防止するために、オンライン申請の際は「登記原因証明情報」と呼ばれる、登記原因が起こったことを証する書面だけはオンラインデータで先に送ることを要求したのです。
そして平成20年当時のオンライン申請の審査は非常に厳しいものでした。
軽微な記入漏れであっても、空登記を防止するために取下げを求められるという事案が起こってしまったのです。
ミスがなければいいじゃないかという声も聞こえてきそうですが、オンライン申請でなく、書面で申請した時よりも当時は審査が厳しくなっていたようです。
そうなると、少しでもリスクを回避するためにはオンライン申請をしない方が良いと考える司法書士・金融機関が出てきたのです。
そして現在も、特にベテランの先生は「オンラインは融通が利かないから危険」と考え、書面で申請をしているそうです。
このように、「空登記の防止」という理由のため、審査が厳しくなりすぎたのがオンライン普及の足かせとなっていました。
現在は、書面であってもオンラインであっても同じような審査がされるため、多くの司法書士はオンラインを用いているということです。
このように、司法書士業界の歴史を調べてみるのも面白いものです。
これからは、オンライン申請も次のステージに突入するはずですので、しっかりと研鑽に励みたいと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
司法書士とブロックチェーン
相続登記や所有者の住所変更登記が義務化されることはこれまでなんどもお話をしてきました。
これは、当事者が所有者のみ或いは、相続人のみで完結する登記であるため、義務化の当事者が少なくなるため可能になったのかもしれません。
ただ、本来、不動産登記の登場場面の代表と言えばやはり不動産取引の場面です。
不動産を売却する・不動産を購入するという場面で司法書士が関与し、登記申請を行います。
具体的には、印鑑証明書であったり、権利証を確認し、登記意思が間違いないことを合わせて確認していきます。
そして登記意思・申請書類に間違いがないことを確認した後、お金の動きにゴーサインを出し、その後お金の流れを確信した後登記申請を行うのが現在の司法書士のお仕事です。
住所変更登記等が義務化になるに伴い、住所変更登記・相続登記などは簡易的なやり方が普及していくことが予想されます。
ただ、一部の登記が簡易化すれば、他の登記も簡易化されることが予想されます。
そこで登場する技術がブロックチェーンと呼ばれるものです。
例えば、不動産取引の場面でブロックチェーンを絡めると以下のような流れになるかもしれません。
・売主買主で売買契約を行う。
・登記に必要な書類等をお互いで確認する。
・取引内容をネットで登録する。
・ビットコインなどの仮想通貨でもって決済が実行される。
・登記申請が同時に完了する。
このようになる可能性があるようです。
そうです、不動産取引の場面で司法書士が登場しないのです。
こうなってしまうと、不動産取引を業務の中心としている事務所は大きな打撃を受けるでしょう。
私のように、成年後見業務であったり、債務整理業務もやっている司法書士であればこのような流れになってもすぐに経営が傾くことはないかもしれません。
ただ、経営が傾いた事務所は必然的にこれらの業務に流れ込んでくることが予想されるので、私としてもより新しい業務を勉強していかないといけないなと感じております。
さて、このように司法書士業務が打撃を受けるというのが、第一の予想なのですが、うまく適応すれば業務を広げていくことも可能なはずです。
例えば、先ほどの場面で、取引の完了画面の登録で司法書士がきっちりと関与していったり、当日来られない売主買主にしっかりと意思確認をしたりと、関与出来得る場面はまだまだ残るはずです。
登記申請などの機械的に処理できる部分に士業が必要なくなる流れを防ぐことは恐らくできないでしょう。
上手くテクノロジー・ITに適応した司法書士になっていきたいと強く感じました。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
所有者不明土地のその先
現在、所有者不明土地が社会的な問題になってきています。
その対策として、相続登記の義務化というのも直近で始まることとされています。
相続登記の義務化に伴って、住所の変更登記であったり氏名の変更登記も義務化されていくことは先日記事で書いた通りです。
ただ、この所有者不明土地問題は、相続登記だけが問題という訳ではありません。
少し、毛色は違うかもしれませんが、有名な「淡路の平和の大仏」これが解体されるニュースも関係があると言えるかもしれません。
この大仏問題、詳しい解説は省きますが、要は大仏を建てた方の相続人たちが大仏を管理しきれなくなり、相続放棄等を経た結果、解体という流れになったようです。
これは、大仏という大きな建物があったために早急な対処が必要となり、解体ということになったのですが、土地だけであればこうはなっていません。
それこそ、相続人・関係者が関わりたくないような不動産となっている土地は多くあるのです。
例えば、共有者が複数になっている土地。
売るにしても貸すにしても関係者が増えすぎた土地には価値がなくなっていきます。
こんな場合に、不動産屋さんが共有持ち分の一部を買い取り、半ば強引に共有持ち分を集めていくこともあります。
これは、あまり良いように感じないという方もおられるかもしれませんが、そうとも言ってられない土地も多いのが現状なのです。
このように共有者が多岐に渡っている不動産でも、土地所有権の放棄制度などが整備されていけばどうでしょうか。
固定資産税の支払いであったり、境界の問題で負担が永遠に続いていくぐらいなら、無料で公に引き取ってほしいと考える方も多くおられるでしょう。
(これは無理かもしれませんが、価値の残っている不動産の放棄であれば、ふるさと納税の扱いにしてあげるなどすれば盛り上がるかもしれませんし。。。)
いずれにせよ、何か問題を抱えている不動産を放置してもその価値は下がっていく一方です。
私の事務所でも、どうしようもない不動産の処分を手伝ってほしいという依頼が来ることがあります。
良くてプラスマイナスゼロというケースも正直多くあります。
この理由はやはり、私のような司法書士であったり、不動産屋さん、場合によっては弁護士さんが登場しなければこういった土地を処分することができないのが現状であるからです。
たとえ、持っている不動産に価値がなくとも、労力をできるだけ少ない形で公に所有権を集中させていく法整備が必要になってきているのでしょう。
この所有者不明土地問題に関連する法整備が今後さらに進んでいくことを期待したいと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
配偶者居住権の登記が。。
配偶者居住権。
民法等の改正により、最近登記ができるようになった新しい権利です。
司法書士業界でも、よく話題になる旬な登記です。
基本的なパターンとしては、夫婦の内の片方が亡くなった時にこの権利が登場します。
例えば、旦那さんが亡くなり、相続人は配偶者と子どもさんという場合を考えてみましょう。
不動産を所有している方が亡くなった場合には、相続登記が必要です。
今回の例では、相続登記のパターンとしては、
1残された奥さんの単独所有
2子の単独所有
3奥さんと子の共有
この三つのパターンが考えられます。
この3パターンの中で、不動産に引き続き奥さんが住む場合、1を選択することが奥さんにとっては1番立場が安定します。
自分の不動産に自分が住むという形になるためです。
ただ、このパターンにはデメリットがあり、奥さんの財産が増加するため、相続税の問題であったり、手続きを奥さんが亡くなった時にもしなければいけなかったりといくつかマイナスの面があります。
では、2のパターンはというと、手続き面、税金面では1に比べるとメリットがありますが、次は奥さんの立場が不安定になってしまいます。
所有者はあくまで子になるため、売却をすることも理論上可能になってしまうためです。
そのため、中間択として3のパターンを選ぶこともこれまで多くありました。
3のパターンのデメリットとしては、仮に売却をする場合などに、当事者が多くなってしまうため、奥さんと子に紛争があった場合に処分できなくなる可能性が出てくることが挙げられます。
そこで配偶者居住権の登場です。
配偶者居住権とは、例のパターンでは、所有者は子に、しかし、奥さんはそのまま住み続けてもいい。さらに奥さんの権利も安定する。という1.2のいいとこ取りのような状態を作り出せる権利です。あくまでイメージとしてはですが。
さて、今回この10日に関して疑義があったので、法務局へ照会をしていました。
当然、他の権利に比べて通達・判例も少ないため、登記が可能かを問い合わせたような形ですが、なぜかかなり怒られてしまいました。笑
これから通達等が出て、改めて確認してみようと思います。
今度はなんとか怒られないように穏便に進めたいと、反省しました。笑
当事務所では、変わった登記、調べても分からないような登記であっても全力で案件にあたることを約束します。
他の事務所でできないと言われた、煙たがられたという方もお気軽にお声掛けください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
夫婦別姓と司法書士
現在、日本の民法・戸籍法では、夫婦別姓を認めておらず、これを違憲だとする判決を求め、時たま裁判所により判断が下されています。
直近では、本日付のニュースでも夫婦別姓を認めない日本の制度は「合憲である」との判断が出されたようです。
合憲との判断が下されるまでの流れとしては、
・3組の男女が夫婦別姓での婚姻を求めるため、夫婦どちらの性を選択するかのチェックでどちらにもチェックをし、自治体に提出。
・当然自治体では受け付けることができなかった。
・3組の内、2組が東京家庭裁判所へ、残りの一組は同裁判所の立川支部に扱いが不当であることを申し出る。
・家庭裁判所としても自治体での扱いは不当ではないと判断。
・特別抗告で最高裁へ、夫婦別姓を認めない現行法は違憲であるとの確認を求める。
・それも認められず、自治体の不受理は問題ないことが確定した。
という大まかな流れです。
日本である法律が違憲かどうかを判断するためには、具体的に何かの事件が起こっている必要があります。
今回は、自治体での不受理の扱いがこれに当たるため、最高裁まで話が進んでいったわけです。
さて、この決定に対しては私は現状では仕方がないのかなと思います。
夫婦別姓を認めるためには、戸籍の制度を大きく変えたりする必要があるためです。
婚姻しなければ、配偶者として相続人となることができません。
これは夫婦別姓の問題の他にも、同性愛カップルにも同じような問題が立ちはだかります。
現行の民法などでは、配偶者は相続などの面で絶対的な地位が確保されています。
ただ、夫婦別姓をするため、同性愛カップルであるために婚姻ができないという方も多くおられるでしょう。
現状ではこれらの場合は、「家族信託」や「養子縁組」といった制度を利用し、財産面の流れだけでも夫婦に近い形を作り出すこともあります。
ただ、当然家族信託では費用がかかりますし、養子縁組については制度趣旨を考えると適していないような気もします。
普通に婚姻できる間柄であれば必要のないことなので、こういった関係性のカップルはやはり今回のような形で世間に声を上げていく必要があるのでしょう。
特に夫婦別姓を求めることについては、世論もかなりついてきたように思います。
司法書士が関与している、商業登記の場面でも、役員さんの婚姻前の氏名を併記することが認められる扱いになってきました。
私たち司法書士などの士業と呼ばれる先生も旧姓を用いることが可能になってきています。
このように、各職業での扱いは実際に変わってきています。
このまま色々な場面で旧姓を利用できるようになっていけば、戸籍法などの制度も変更に向かって舵を切るかもしれません。
こういったニュースにも注目していきたいなと思いました。
当事務所では、前述の家族信託を用いた同性愛カップルなどの方への信託契約書のご提案も行えます。
気になった方は一度ご連絡くださいませ。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
相続登記の義務化。住所変更も??
相続登記が義務化されることはこれまでもお話をしてきたとおりです。
具体的には、
・自己のために相続の開始があったこと
・対象の不動産の所有権を取得したこと
を知った時から3年以内に相続登記をしなければならないとされることになります。(遺贈なども含まれる)
この「自己のために相続の開始があったこと」については、私のホームページ内でもお話したことがあります。
相続登記の場面ではなく、相続放棄の場面ですが。
相続放棄の申述は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
相続放棄については多数の判例もあるため、相続放棄の義務化がなされた後は、こういった判例も生かされていくのではないでしょうか。
さて、相続放棄の場合は、この3か月以内に相続放棄をしなければ相続放棄ができなくなる、すなわち相続するしかなくなります。
では、今回の法改正である、相続登記の義務化ではどうかというと、「10万円以下の過料」を科される扱いとなるようです。
10万円。。。痛いですね。
相続登記については、所有者不明土地を解消するために多少の罰則は必要かと思います。この10万円の額がどうかは別として。
ただ、今回は追加情報として、相続登記だけではなく「氏名変更の登記」であったり「住所変更の登記」も義務化されるようです。
司法書士のイメージとしては商業法人登記に近づいたように感じます。
商業法人登記は、例えば代表者の住所変更であったり、会社の本店が変わった場合には「2週間以内」に変更の登記をしなければいけないことになっています。
今回の改正により不動産登記に関しても「変更があればすぐに登記」という扱いに変更となるわけです。
私たち司法書士としては悪い話ではありません。
当然、住所変更などの登記件数が増えるわけですからね。
ただ、これは前回の相続登記義務化に関しての記事でも申し上げましたが、義務化には簡略化もセットになるべきです。
例えば、住所・氏名の変更をすれば自動若しくは自分自身で簡単に登記ができるようなシステムにいつかはなるでしょう。
そうなると私たち司法書士の仕事はむしろ減少することも十分にあり得ます。
そうなった場合に、消えていく司法書士事務所も当然増えていくでしょう。
しかし、私たちの仕事は本来、「誰にでもできるはずの仕事を代理で行う」仕事です。
そんな司法書士業界の中でも私にしかできない仕事を増やしていこうと改めて感じた今回の法改正でした。
法改正は2024年施行予定です。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
清算結了の抹消・・・続き
以前お話しました、株式会社の清算結了登記の抹消登記が無事完了しました。
結局、添付書類としては、以下のとおりでした。
・上申書
・債務が残っていることの証明書
・委任状
以上です。
通常の清算結了登記の抹消登記のケースでは、清算業務が残っていることの証明として「財産が残っていることを示す」証明書を添付します。
例えば、法人名義の不動産がまだ残っていることを示す不動産登記簿の謄本。
法人名義の通帳口座の通帳などがこれに当たるでしょう。
ただ、今回は、対象会社には債務しか残っていませんでした。
前回も少しお話したように、債務超過の会社が会社を畳む場合は、特別清算や法人破産などの債務整理の手続きを経る必要があるため、司法書士だけの関与ではできないことがあります。
しかし、多くの司法書士が関与している会社はほとんどが中小企業であり、そこまで大規模な清算業務をすることはありません。
プラスの財産があれば株主に分配し、負債があっても代表者へ債務引き受けを行い、会社としての債務は0にして清算業務を完了させるのです。
今回のケースも基本線はこの債務引き受けパターンでした。
よって、一度目の清算結了をした時は、残債を債務引き受けしたことを株主総会で承認してもらい、清算業務を結了させていました。
ただ、その後に他の金融機関からの借り入れがあったことが判明し、清算結了登記の抹消が必要となったのです。
一度清算結了登記をした会社に債務が見つかった・・・
つまり、ほぼ間違いなく「債務超過」状態であるのです。
よって普通に抹消登記を申請しても登記は通りません。
そこで、「上申書」の内容が重要になってきます。
要は、「清算結了段階で、会社に債務が残らないこと」を上申する必要が出てきます。
その理由は様々考えられます。
可能性としてはかなり低いですが、借金だけでなく、それを上回るプラスの財産も見つかった。これもあり得ます。
他には、債務は見つかったが、金融機関が債権放棄をしてくれることが決まっている。これも理屈としては考えられますが、放棄するならわざわざ会社を復活させることを金融機関は求めないでしょう。
次に考えられることは、見つかった債務を全額代表者へ引き受けてもらい、法人の債務を0にする。これが今回パターンでした。
めったにない登記でしたが、今後もあるとすればこのパターンかなと思います。
上申内容としては、
・対象法人に債務が見つかったこと。
・この債務は代表者への債務引き受けがされることが金融機関との協議で決まっていること。
・よって対象法人が債務超過になることはないこと
以上を踏まえた上申となります。
登記申請の際、債務があることを示す証明書の他に、債務引き受け契約書の添付も求められるのかなと思いましたが、そこまでは求められず、無事登記が完了しました。
もし同じような案件にあたった方がおられたら、参考になさってください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
債務整理の方針が決められない方
債務整理の手段には、いくつかの手段があることはこれまでにも何度もお話をしてきました。
基本的には、債務額であったり、収入額等等で判断し、任意整理・自己破産・個人再生の中から依頼者に合った形で手続きを決定していきます。
具体的には、総債務額を36回〜60回で割った数字を出し、3年から5年で全ての債務が返済可能かを判断します。
返済が可能であれば、任意整理で。
それが不可能であれば、自己破産等の裁判所を通した手続きを検討していきます。
っというように、依頼時に提供していただいた情報から、受任時までに手続きを決定するのが原則です。
ただ、昨今の状況を考えると、依頼時に今後の見通しが立たないという方も多くおられます。
そういった場合は、司法書士に依頼することができないのか。
当然そんなことはありません。
今挙げた、任意整理・自己破産・個人再生、どの手続きであっても最初の作業は同じです。
各債権者に対し、司法書士が手続きに介入したことを通知(受任通知)し、各債権者は返答として、債務額の確定を行い、司法書士に通知します。
この一連のやり取りに、1ヶ月〜3ヶ月ぐらいかかります。
これはどの手続きを選択しても同じです。
つまりこの間に、見通しをある程度立てるという後出しでの手続き選択も可能なのです。
特に最近は、1ヶ月2ヶ月で社会情勢が大きく変わります。
ただ、1ヶ月経ってから、2ヶ月経ってから司法書士に依頼すると、さらにそこからの1ヶ月で収入が大きく変わってしまうこともあり得ます。
債務整理で大事なことは、素早くかつ適切に手続きを決定することなのです。
そのためにはまず、破綻する前に司法書士へ相談してみましょう。
1ヶ月早く来てくれていれば、破産しなくて済んだのに。という方も多くおられます。
相談が遅れれば遅れるほど、取りうる選択肢は狭まります。
巷で認識されているほど自己破産にはデメリットが少ないのですが、それでもやはり任意整理で済む方は任意整理を選択されます。
ご自宅があるなどの自己破産をどうしてもできない方はもちろん、そうでなくても「破産」という響きは依頼者に大きなダメージを与えます。
どうしても破産はしたくない、裁判所の手続きは怖いという方は1日でも早く専門家へ依頼しましょう。
相談にさえ来ていただければ、取り敢えず直近の返済を止めながら、手続きを選択していくことが可能です。
どうか生活が破綻し切る前に当事務所の無料相談をご利用ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。