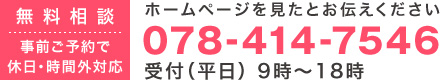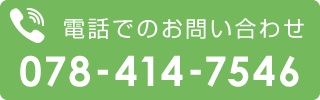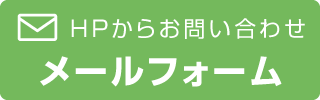Author Archive
まだ過払い金はあるのか。
神戸で債務整理業務を行っておりますが、やはり過払い金が発生するケースはかなり少なくなっています。
このHPの記事でも説明しているように、過払い金が発生している取引は少なくとも2010年以前に取引を行っていた方でなければ発生しません。
また、この過払金には時効があり、完済から10年で時効消滅してしまいます。
つまり、2010年以前に取引があり、かつ、完済している場合は2010年9月以降の完済でなければいけません。
このケースは現在かなり少なく、私も過払い金の返還訴訟を行うことが少なくなっています。
しかし、この度、運よく過払い金が発生しているお客様がいらっしゃいましたので、手続きを進めておりました。
受任は6月の終わりでしたが、この社会情勢ということもあり、業者からの履歴開示・裁判所の期日設定、全ての工程がいつもよりかなり遅くなっていました。
ようやく9月になり、第一回目の期日があったので、明石簡易裁判所へ行ってきました。
そこで、久しぶりの過払金返還請求ということもあり、自分の備忘録も兼ねて、過払い金返還の流れをご説明したいと思います。
この先の過払い金返還請求は必ず時効との闘いなので、もしご自身でしたいという方がおられれば、参考になさってください。
過払い金の請求にあたって第一のステップは、「そもそも過払い金が発生しているのか」を調査することから始まります。
私たち専門家が受任する場合は、「受任通知」を発送する必要があるため、受任通知の書類と合わせて取引履歴の開示を求めます。
もし、ご自身で手続きを行う場合は、業者に連絡し、「取引履歴を開示してください」と言えば開示してくれるはずです。
注意点としては、もし債務が残っている時点で履歴を取り寄せた場合には、以降の支払いが債務者にとって不利に働くこと。昔の履歴が開示されない場合があること。
このような場合は、速やかに専門家への依頼をお勧めします。
履歴が開示されるまでには少し時間がかかります。1か月ぐらいはかかるので、時効ギリギリの場合は専門家に依頼する方が無難でしょう。
開示された履歴を、法定利息内で計算をし直す「引き直し計算」が次の工程となります。
この時点で過払い金が発生していた場合に初め、て返還訴訟の工程へと進みます。
この時点での注意点は、「取引期間内に、完済をしていた期間がある」「返済を遅れたことがある」場合です。こういった場合、業者は過払い金の返還額を少なくしようと強気で交渉してきます。
よって、このようなケースでも専門家への依頼をした方が、返還額が大きくなる可能性が高いです。
そして、いよいよ返還請求を行いますが、提訴するかしないかで二つに分かれます。
全ての業者とは言えませんが、一般的には、提訴した方が返還額が多くなります。(今回受任したケースでも迷わず提訴しました。)
提訴しない場合は、こちらから業者へ連絡し、FAXや電話等で返還額を交渉していきます。
専門家が介入する場合は、金額はこちら主導で進んでいきますが、個人の方が行う場合は、業者主導になってしまいます。
ご自身でなさる場合は、強気での交渉を心がけてください。
専門家に依頼すると当然報酬が発生しますが、返還される金額は専門家に依頼した方が多くなりやすいため、お手元に残るお金は専門家に依頼した方がむしろ高くなることも多くあります。
そして、多くの場合では、提訴しても裁判が最後まで進むことはなく、和解が成立します。あくまで提訴するのは交渉を有利に進めるためなのです。
提訴した場合、裁判所へ出頭する必要はありますが、相手方が来ないことも多く、次回期日の調整を行う程度です。
ご自身で請求を行う場合でも、提訴というカードを取ることをお勧めいたします。
過払い金について知りたい、借金が多くて辛い、こういった方は是非一度ご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
神戸市中央区に新たな体育館が!!
神戸市は、三宮の再整備に力を入れていますが、その一環として、磯上公園に体育館が新設されるそうです。
利用開始予定は2022年夏ごろを予定しているそうです。
現在の磯上公園にある、テニスコートはそのままで、グラウンドのある場所に体育館が建設されるとのこと
神戸市による三宮の再整備と言うと、市の勤労会館や生田文化会館を新中央総合庁舎に集約することとなっており、これにより文化面の集約が図られています。
文化面は総合庁舎へ、スポーツ面は磯上公園へ、神戸市中央区の施設が集中していくようです。
このニュースについてですが、私のような馬鹿な若者にとっては、楽しみの方が大きいです。
まだ新たな体育館にどのような施設が入るのかは知りませんが、「大きなバスケットコートがあれば、Bリーグの試合があるのかな」とか、
「大規模なジムがあれば楽しそうだな」とか、色々考えてしまいます。
しかし、特に文化面での反対意見も私はよく耳にしました。
前職で、コーラスをしている方がおられたのですが、その方は「生田文化会館で十分で、他にお金をかけるべきところがあるはず」とおっしゃっていました。
確かに、新たな設備・施設は、既存の施設で満足している方々にとってはあまりいい印象ではないのでしょう。
神戸市としても、こういった方々への説明はもっとしていくべきだったのではないかと感じました。
新しいことを始めるには必ず賛成意見も反対意見もありますが、始める以上、市民を説明・説得する力は政治家に必要な力だと思いました。
しかし、スポーツバカ兼明石市民という勝手な立場から言えば、今回の一連の再整備案はどれもワクワクします。
これからどんな街になっていくのか見ていくのが楽しみです。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
140万円以上の借金は司法書士には扱えない??
司法書士は、法務大臣からの認定を受けると、簡易裁判所での代理権を得ることができます。(認定を受けた司法書士を認定司法書士と言います。)
現在、債務整理を行っている司法書士のほぼ全てがこの認定司法書士と呼ばれる専門家です。
しかし、この認定司法書士となっても、全ての裁判案件を代理できるかと言えばそうではなく、訴額140万円を超えない場合に代理人となることができます。
このことが「司法書士は140万円を超える債務整理はできない」と世間から認識されている理由です。
この認識は正しいのですが、140万円をどのように計算するのかについては正しく認識されていないように思います。
例えば、総債務額が300万円である債務者がいた場合、司法書士が手続きに介入できない場合は以下のような場合です。
・1社(一人)で、140万円を超える債権者がいる場合。
・140万円を元金のみで超えている場合。
・債務整理の手段の中で任意整理を利用する場合。
この全てを満たした場合に初めて、司法書士が債務者を支援することができなくなります。
いずれか、ではなく「全て」です。
実は、この全てを満たすケースというのはあまりありません。
例えば以下のような場合。
・総債務額が300万円であっても、3社からの借金であり、各債権者から100万円ずつの借り入れであった場合。
・債務額が140万円以上であっても、元金は120万円で、遅延損害金を含めて初めて140万円を超えている場合。
・任意整理ではなく、自己破産の手続きでの解決を図る場合。(書類作成での支援)
こういったケースでは、司法書士が債務整理業務を行うことが可能となるのです。
つまり、司法書士が債務整理を行うことができる範囲というのは、それほど狭くはないのです。
また、一般的に、司法書士と弁護士がどちらも行う業務があった場合、司法書士に依頼をした方が費用的に安く済むことが多いです。
債務整理業務の最大かつ絶対的な目標は「債務者の生活再建」であり、費用はできる限り安く抑えるべきだと私は思います。
「私は200万円の借金があるから弁護士にしか頼めない」「破産するには弁護士に頼むしかない」
こういったことを考えている方は、ご自身の状況をもう一度考えてみてください。
司法書士に頼んでも、解決できる問題ではありませんか?
もし、自分の状況が司法書士案件か、弁護士案件かで悩まれている場合は、是非ご連絡ください。
万が一、弁護士案件であった場合でも、費用が発生することはありません。
ご希望があれば、弁護士の先生へ引継ぎすることも可能です。
特にこの債務整理については迅速な対応が解決への糸口です。
一人で悩まず、是非お声掛けください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
債務整理と司法書士~司法書士は債務整理の専門家~③
前回に引き続き、債務整理業務と司法書士の関りについてお話していきます。今回で最終回です。
前回は、司法書士が簡易裁判所の代理権を取得するまでをご説明しました。
司法書士が簡易裁判所の代理権を取得したことに加え、この平成14~15年以降、さらに債務者にとって有利な流れとなりました。
平成15年~16年、最高裁で画期的な判決が出されたのです。
それは「みなし弁済」というものが事実上認められないことを示すものでした。
詳しい説明はしませんが、これによりグレーゾーン金利がなくなり、法外な利率での借金が減少していったのです。
それどころか、「過払い金」が発生する債務者も多く、これは貸金業者にとっては大きな逆風となりました。
この過払い金の発生により、司法書士・弁護士業界はかなり潤うことになり、過払い金に特化した事務所まで登場するようになりました。
しかし、この過払い金は理論上、永遠に発生する業務ではありません。当然このバブルは終わりを告げ、過払い金に特化した多くの事務所は姿を消すことになります。
この過払い金バブルには、良い点も悪い点もありました。良い点は、「法律の専門家」として司法書士が社会的により認知されるようになったという点。
逆に悪い点は債務者の生活再建よりも、利益率の高い業務に特化した事務所が多くなってしまい、「簡裁代理権=過払い金」のようになってしまった点です。
これまでの全3回で述べてきたように、司法書士が簡易裁判所の代理権を得るまでの道のりは、常に債務者の生活再建と共にありました。
事実、過払い金の請求業務はほぼ姿を消しており、本来の債務整理業務がほぼ100%になっています。
過払い金バブル時のみ、簡裁業務を行い、債務整理を行っていない司法書士も多く、それは専門家としてふさわしくないと思います。
専門家をお探しの時は、是非、利益率の良い任意整理・過払い金だけを行う事務所ではなく、「破産」「個人再生」等の手段から総合的に手続きを選択してくれる事務所を選んでください。
最後に、現在多い債務整理のパターンをお話ししたいと思います。
これまで述べたように、法外な利息により苦しむ債務者は減少しております。
しかし、現在は、昔に比べ「借金をするハードル」が低くなっています。
学生でもカードが作れたり、ネットでの申し込みでクレジットカードを作れたり、リボ払いが浸透したりと、以前よりも借金をする経緯が増加しています。
特にリボ払いやネットショッピングの分割払い等は借金をしている感覚すらありません。
事実、非常に年齢が若い方や、主婦の方などのご依頼が増えています。
これが現在の債務者を取り巻く環境です。
以上で債務者と司法書士の歴史についてのお話を終わろうと思います。
債務整理手続きは恥ずかしいことではありません。是非、できる限り早いご相談をしてくださるようにお願いいたします。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
半沢直樹と司法書士①
今年話題のドラマと言えば、やはり「半沢直樹」でしょう。
私も、前作からしっかりハマってしまい、今作も欠かさず毎週観ております。
さて、今回は、司法書士がこの半沢と関係がある仕事だということをお話ししようと思います。
現在のドラマの第一章。この第一章では、「企業買収」が一つの大きなテーマとして登場していました。
スパイラルが電脳から買収されようとしている所を、半沢が様々な工夫を凝らし、乗り切っていきます。
そして、この買収の対応策としてまず考えられた方法が「新株発行」という手続きです。
まず、そもそも企業買収とは、買収したい企業の株式(正確には議決権)の過半数を取得することを指します。
その対策として、株式の母数を増やすことで、過半数の取得を妨げようとするのが新株発行です。
現在、株式取引をされている方はお分かりかと思いますが、一般的に株式取引と言えば既に市場に出ている株式を売買することで成り立っています。
しかし、この新株発行という手続きでは、文字通り新たに株式を発行します。当然ですが、発行するだけではまだ誰が所有するかは決まっていません。
そこでこの新株の買い取りに手を挙げたのが、ドラマ内でのフォックスでした。この企業買収を防ぐために助けてくれる企業のことを「ホワイトナイト」と言います。
と、ここまではドラマのあらすじのようになってしまいましたが、この新株発行が予定通り進んでおれば、司法書士がこの手続きの最後で現れます。
何故かと言うと、この新株発行には「登記」が必要だからです。
新株を発行する場合、資本金の額と、発行済株式の総数に変更が出るため、登記をしないといけないのです。
具体的な必要書類は以下の通り。
1、取締役会議事録
2、総数引き受け契約書
3、払い込みがあったことを証する書面
4、資本金の額の計上に関する証明書
5、委任状
です。1,2については、ドラマで登場しています。
まず、1は、瀬名社長(尾上松也さん)が株式の発行について会議をしていたあの場面での議事録がそれに当たります。
2は、山崎銀之丞さんの名演技があった社長室での場面。押印を促した書類が恐らくそれにあたります。
そして、3、4は入金があったことを示す証明書と、その入金の内いくらを資本金として計上するかを示す証明書です。
つまり、瀬名社長の押印が済んでいれば、フォックスが入金し、3,4の書類はすぐに出そろいます。そして、それらの書類を司法書士に渡し、登記申請。
という流れになっていたはずです。(結果はご存じのように、2の契約の前に新株発行は流れましたが・・・)
半沢の活躍により、司法書士の出番もなくなってしまいました・・・
しかし、このように会社の法務と司法書士は密接に関連しています。
会社の構成を変更する、新たに株式を発行する。こういった場面は司法書士の主戦場です。
また、第二章の中でも、司法書士に密接する業務があるため、今後またお話ししたいと思います。
それでは楽しみに週末を待ちたいと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
債務整理と司法書士~司法書士は債務整理の専門家~②
前回に引き続き、司法書士が債務整理業務の専門家とされるまでの歴史をお話ししていこうと思います。
前回は、司法書士が団体として多重債務問題にあたるまでの流れを説明しましたが、今回はその続き、平成5年ごろからです。
平成5年ごろ、各消費者金融業者において、「無人契約機」が流行します。テレビでのコマーシャルも多く放映されるようになり、今でも記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
この無人契約機により、機械だけが設置された店舗へ行き、カードが即日発効され、即日融資が受けられるようになりました。
貸金業者はこれにより、人件費の削減はもちろん、債務者の借金への心理的ハードルを下げることに成功し、勢力を拡大していきました。
それと同時に、多重債務に陥る人の数もどんどん増えていったのです。
そして、司法書士業界としては、平成10年から、弁護士業界と協力し、全国各地で上限利率の引き下げ、業者による過度な貸し付け(過剰融資)の禁止を求める運動を行いました。
相談会を開き、署名活動を呼びかけ、被害者の会を作り、確実に社会への訴えかけをしていったのです。
これまでは、主に個人の債務者を救済するべく活動していた司法書士・弁護士ですが、平成11年ごろには「商工ローン問題」が社会的に知られるようになります。
商工ローンは、個人消費者への貸し付けをせず、自営業者や中小企業への貸し付けを主としています。
商工ローンの詳しい仕組みは割愛しますが、高い利率・過度な取り立てが原因で被害を受ける債務者が多い点はこれまでと同様でした。
司法書士・弁護士としては、この商工ローン問題に対しても対応をしていきました。全国各地での運動の成果もあり、上限利率の引き下げを行うことができ、一定の成果を上げます。
まだまだ上限利率は債務者を救うほど低くはならなかったものの、司法書士の運動が社会を変えた、その点において、確かな実績となりました。
しかし、まだまだ消費者金融の勢いは止まることなく、被害を受ける債務者は増えていきます。
またこのころになると、消費者金融からは既に借りられない状態になってしまう債務者も増えてきました。
そうなると出てくるのがいわゆる「闇金」です。とんでもない利率での貸し付けが違法に行われ、大きな社会問題となります。
平成15年にようやくヤミ金対策法が成立しますが、そもそもの原因は闇金ではありません。
消費者金融による過度な貸し付け・高い利息を解決する必要があったのです。
平成14年ごろ、司法書士の関与としては、破産・調停・個人再生等の手続き書面の作成を行っていました。
債務者を救済する法整備が整っていなかったこともあり、司法書士が相手をする債務者は「既に借金で首が回らない状態」の債務者でした。
一方、弁護士は「任意整理」という方法での債務者救済を行っており、これは破産等に至る前に対処できる方法です。
この当時、司法書士には裁判の代理権がなかったため、任意整理を行うことができず、業務内容に違いが起こっていました。
しかし、サラ金・商工ローン・闇金問題に対して、司法書士は弁護士と協力して解決にあたっていました。
その実績が認められる形で、平成14年、司法書士にとっては画期的な法改正がなされます。
それがいわゆる「簡裁代理権の取得」です。これにより司法書士は認定を受ければ裁判の代理権を取得することが可能となったのです。
この法改正により、司法書士は弁護士と同様に任意整理により債務者を救済することができるようになり、今日に至るのです。
本日は、司法書士が裁判代理権を取得するまでの流れをお話ししたところで終わりとします。
次回は、最終回、消費者を取り巻く環境がその後どう変わったかをご説明したいと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
債務整理と司法書士~司法書士は債務整理の専門家~①
債務整理手続きの具体的な流れについてはHP内に記載していますが、今回はそもそも司法書士がどのようにして債務整理業務と関わるようになったのかをお話ししていこうと思います。
これを読めば、どうして司法書士が弁護士と並び債務整理問題の専門家として認知されているかが分かるはずです。
そもそも、債務整理が必要となったのは、昭和30年代~40年代ごろ、サラリーマン金融(サラ金)が巷に浸透してきたのが始まりです。
その当時は貸金業法も整備されておらず、貸出利息は70%を超え、100%に近いものも多かったそうです。
現在、消費者金融の利率は15%前後が多いことを考えると、当時の利率が途方もなく高いことが分かると思います。
当然、これほどの利率になると、「返済するために借金をする」という自転車操業のような形になり、多重債務状態に陥る債務者が激増します。
しかし、このサラ金が社会問題として認知されたのは昭和50年代の終わりになってからです。
サラ金業者による過度な取り立てにより被害を受ける債務者がマスコミにより報道され、ようやくこの問題が社会に認知されたのです。
問題が認知されたことにより、旧貸金業法が制定され、このサラ金問題は一旦沈静化しました。
この当時、問題にあたっていた専門家はその多くが弁護士でした。
また、一部の司法書士はこの時点で裁判所類作成等の業務を通じ、債務者問題に取り組んでいました。
つまり司法書士は弁護士と同様、非常に早い時点で多重債務問題に取り組んでいたのです。
次に多重債務問題が顕在化したのは、平成2~3年ごろ。
しかし、これはあくまで「顕在化」した時期であり、問題は先ほど書いた昭和60年代から進行を続けていたのです。
旧貸金業法制定時には、「みなし弁済」という制度が盛り込まれており、これは一定の条件を満たせば、利息制限法を超えた利息が認められるという制度です。
この制度を悪用することにより、貸金業者は利息制限法を超えた高金利の利息を得ていたのです。
しかし、先ほどの段落で説明したように、昭和50~60年代のサラ金問題は一度沈静化しました。
問題は沈静化したが、進行していた。一見矛盾するようですが、そうではありません。
その理由は「バブル景気」です。社会全体が好景気であったため、この債務者問題が顕在化しなかったのです。
そしてバブルが終焉した平成2~3年で再び多重債務問題として社会が認知したのです。
この時期、司法書士は個人での取り組みの枠を超え、組織的に対応を始めました。
青年司法書士会等の司法書士団体が弁護士団体とも協力しながら、各地で相談会・交流集会を企画していったのです。
このように、専門家団体としても司法書士は非常に早い段階からこの問題にあたっていたのです。
今回は、平成2~3年までの多重債務問題の発生から、司法書士が専門家団体としてこの問題に取り組むまでの流れをお話ししました。
次回は、この先、貸金業者が最も力を持っていた平成10年ごろのお話からしていこうと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
第三者が遺産を使っている場合の相続-2(賃貸借・使用貸借・無断使用)
前回に引き続き、相続財産に含まれる不動産を第三者が使用している場合のお話しをしていこうと思います。
賃貸借の次に多いパターンとしては「使用貸借」が挙げられます。
賃貸借が第三者使用に対価が発生するのに対し、使用貸借は無償で第三者が使用しているのが特徴となります。
基本的には、使用貸借は使用目的・期間を定めて契約を結びますが、そういった決め事をしないで結ばれていることも多いです。
その理由は、使用貸借が多くの場合、親族や友人などの関係の中でよく用いられるものであるからです。
つまり、被相続人である貸主と借主の間は親密な関係であったということがほぼ全てのケースで当てはまるでしょう。
しかし、相続人と借主の間にも親密な関係があるかと言えば必ずしもそうではありません。
そこで、使用貸借の対象である不動産をどのように取り戻したいと思った場合、どのようにすればいいかを解説していこうと思います。
まず、使用貸借の終了事由は民法597条、598条に定められています。箇条書きにすると、
1、期限を定めた場合はその期限の満了
2、目的を定めた場合は、目的に従った使用・収益終了時、若しくは使用・収益に足りる相当期間経過時
3、借主の死亡
4、目的及び期間を定めなかった場合、貸主からの解除
以上です。注目していただきたい点は、貸主の死亡により終了しないということと、貸主は解除をすることができるという点です。
この決まりがあるため、使用貸借は永遠には続きません。
よって、これらの終了事由が生じれば、相続人は目的物の返還を請求することができます。(相続人の過半数で請求可能だと解されています。)
しかし、前述のように、使用貸借は契約書等を作成せずに結ばれていることも多く、目的・期限の定めがあったかどうかで紛争が起こることもあり、この点は注意が必要です。
契約について紛争が起こった場合は専門家への相談を強くお勧めします。
また、使用貸借契約があったと借主が一方的に主張しているが、権限を証明する資料が何もないということもあり得ます。
これが、第三者が不動産を使用しているパターンの最後である、無断使用の場合です。(単に勝手に不動産を使用されている場合も含みます)
その場合は、相続人として、不動産の占有者を無権限者として妨害排除請求をすることも可能です。
無権限者への請求を行う場合は保存行為となり、相続人の過半数の足並みを揃える必要もなく、各相続人が単独で請求を行うことが可能です。
ただし、万が一無権限者が不動産登記を不正に行っていた場合、その所有権移転全てを抹消するには相続人の足並みを揃える必要があるため、司法書士・弁護士に速やかにご相談ください。
以上が第三者が相続不動産を使用している場合の対処法です。特に今回説明したケースは紛争になる場合が多いです。
少しでも疑問がある方は是非お問い合わせください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
第三者が遺産を使っている場合の相続-1(賃貸借・使用貸借・無断使用)
相続対象不動産の中には、被相続人の方が使用していなかったものも当然含まれます。
遺産分割協議が終了し、すぐに遺産を承継する人が決定すればあまり大きな問題とはなりませんが、遺産分割協議が長引くと、その間に発生した問題をどのように解決すべきか悩むことになります。
今回は遺産分割協議が終わる前に発生し得る問題について解説していこうと思います。
第三者が被相続人の不動産を使用している場合、その理由は賃貸借・使用貸借・無断使用の三つが多いでしょう。
まず、賃貸借の場合、以下の問題が発生する可能性があります。
1、賃料債権はどのように請求すればいいか。
2、契約更新をどのようにすればいいか。
3、解約の申し入れがあったらどのようにすればいいか。
4、隣地との境界に紛争が発生した。
まず、賃料についてですが、これは当然、相続人間で分けられることになります。
しかし、相続人が複数いる場合、賃借人が相続人それぞれに相続分に応じて賃料を支払うのは負担であり、現実的ではありません。そこで、対応策としては、とりあえず相続人間で代表で賃料を受け取るものを決定し、賃借人に通知しましょう。
この時の注意点としては、あくまで遺産分割協議が整うまでの仮の全額受領であるため、他の財産と混じらないように管理しておくことが必要です。
次は、契約の更新についてです。これは対象不動産の種類と契約期間によって扱いが変わります。
賃貸借契約には「短期賃貸借」というものがあり、この短期賃貸借に当てはまる賃貸借は「管理行為」という扱いになります。
具体的には、
一 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
三 建物の賃貸借 3年
四 動産の賃貸借 6か月
とされており、この期間内の賃貸借であれば、管理行為と扱われます。(民法の改正により、これを超える期間であれば、この期間に短縮されます。)
また、この管理行為という扱いになれば、相続人は過半数の意思決定でこれを行うことができます。
結論を言うと、更新については、相続人の過半数の意思決定により行うことができるのです。(賃料の変更についても管理行為であるため同様)
逆に、居住用不動産を建てるために、相続財産に含まれる土地を新たに貸す場合は、管理行為に当たらず、相続人全員の意思決定が必要となります。
このように財産の性質を大きく変えてしまう行為を変更行為と言います
続いて、解約の申し入れについても管理行為という扱いになり、結論は更新と同じです。
最後に、境界で紛争があった場合ですが、これまでの流れを考えるとお分かりの方もおられるかと思います。
相続財産を管理する行為ならば、過半数。
相続財産を変更する行為であれば、全員の意思決定。
これが大きな考え方なので、境界の紛争を解決し、境界を確定させる行動は「変更行為」に当たります。
つまり相続人全員で行う必要があります。しかし、どうしても参加しない相続人がいる場合は、その相続人も「被告」という扱いにし、法的手続きをすることが可能です。
以上が相続財産を他人が使用しているケースで一番多い、賃貸借の場合の論点です。
残りの使用貸借等については後日またお話ししていこうと思います。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。
印鑑証明が取れない??~相続人が海外に住んでいる場合~
昔と比べ、海外が身近になった現代では、相続人の一部の方が海外に住んでいるというケースもかなり増えてきました。
日本は「ハンコ文化」であるとよく言われます。
段々と脱却が図られている業界もあるようですが、私たち司法書士が相手にしている不動産登記の世界はまだまだこのハンコ文化から脱却できそうにありません。
このハンコ文化が足を引っ張る場面はいくつかありますが、特に面倒なのは相続登記の場面です。
相続登記を遺産分割協議書を用いて行う場合、「相続人全員の実印+印鑑証明書」の添付が必要となりますが、相続人の中に海外在住の方がいると、この印鑑証明書の提供ができません。
そうすると、「印鑑証明書に代わる公的証明書」が必要となります。
海外在住者の在住国にも拠りますが、その場合、「サイン証明書」若しくは「サイン拇印証明書」というものが印鑑証明書の代わりに用いられることになります。
これらの証明書の取得方法は以下のようになります。
1、海外在住の方へ郵送で遺産分割協議書等の書類を送る。
2、海外在住の方がそれを持って、日本領事館・日本大使館へ行く。(要事前予約)
3、係員の前で署名及び拇印を押し、本人のものであることを示す証明書を発行してもらう。(手数料は1700円程度)
持ち物は領事館・大使館ごとに若干異なるようですが、パスポートと住所を示す資料であることが多いようです。
そして領事館等で取得した書類を日本へ送り返し、それをもって登記を申請するという流れになります。
当然ですが、相続人が全員日本にいる場合に比べ時間がかなりかかってしまいます。
後に不動産の売却等がある場合は、期間に注意して速やかに手続きを進めましょう。
また、相続登記には「在留証明書」も必要となる場合があり、これも同じく大使館・領事館での発行となるのですが、本籍地入りで発行する場合、戸籍謄本が必要となる点が注意事項です。
スムーズに進めるためには、サイン証明書を発行するために書類を郵送する際に戸籍謄本も一緒に郵送しておくことが必要です。
当事務所では、海外在住の方を含んだ相続案件も多くの経験があります。特に、相続手続きを急がなければいけない方は是非お問い合わせください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。