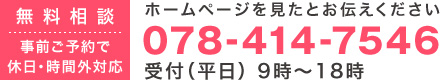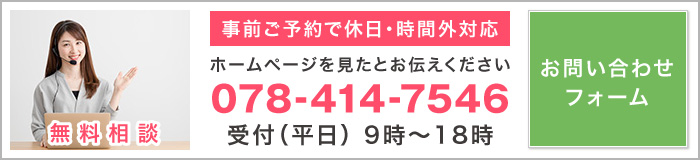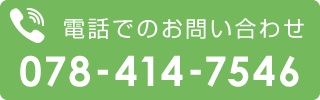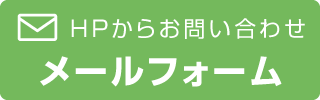司法書士は、成年後見など認知症の方、高齢者の方の財産管理を多く受任している士業です。
家庭裁判所から選任される数は、弁護士などの他の士業よりも司法書士が多いのが現状です。
つまり、高齢者・認知症の方と一番多く接する士業が司法書士と言っても過言ではないかもしれません。
さて、高齢者の方々と多く接する場合、避けては通れないのは、被支援者の死です。
人間だれしも最後は死ぬことになります。
では、自分が死んだ後は誰が葬儀の手配や、相続の手続きをするのでしょう。
例えば、同居の親族がいる場合。
多くの方は親族の手によって葬儀が執り行われ、相続手続きについても相続人が事務処理をしていくことになるでしょう。
ただ、司法書士等の士業が財産管理人となっている方は、相続人・親族の方からご協力が得られないというケースも多くあります。
この場合は、どうなるのでしょうか。
まず、成年後見業務は、「被支援者の死」によって業務が終了するという法設計になっています。
つまり、認知症の高齢者が亡くなった時に、司法書士の業務権限は終了するのです。
司法書士は業務権限がなくなるので、権限のある方へ相続財産を引き渡すことにより業務を完了させて終わりなのです。(具体的には、相続人へ通帳等を引き渡して終了)
そうです、葬儀の手配であったり、相続手続きを成年後見人がそのまま行うことはできないのです。
とはいっても、先ほど言ったように、親族のご協力が得られない場合もあります。
その場合は、あくまで緊急事態ということで葬儀等の事務処理を行うことになります。
ただ、この場合の事務処理はあくまで最低限のことしかできません。
被支援者が生前に考えていた通りに事務ができるとは限らないのです。
例えば、先祖代々の墓があったが、その存在を知るものが被支援者だけだった。
死後の事務については具体的に決めていなかった。
という場合。
この場合、最悪は、無縁納骨堂へ・・・ということも十分に考えられるのです。
どうすればこれを回避できるのかというと、現状は二つの方法が考えられます。
一つ目は原則通り、親族の方から依頼を受けて、相続手続等を行う方法です。
相続人の方は、被支援者とは関わりたくないが、やらないといけないことは仕方ないというスタンスの方も多く、案外依頼を受けることも多いです。
二つ目は、死後事務委任契約をあらかじめ締結しておく方法です。
これは認知レベルが低下しきる前にしなければなりません。
しかし、きちんと契約をすることができれば、自分の思ったように葬儀等を行うことができるため、最後の意思表示を確実に実現することができます。
この死後事務委任契約、まだまだ普及しているとは言えないような状況です。
ただ、認知症・高齢者の方と多く接する司法書士の立場からすると、もっと利用されるべき制度だと考えます。
自分の最後の意思を実現させたい、親族には迷惑を掛けたくないという方は是非当事務所までご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。