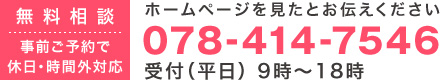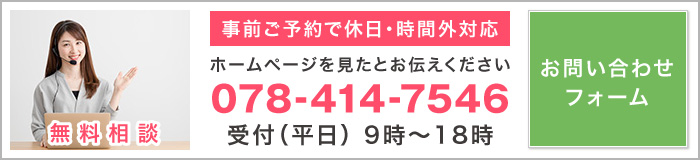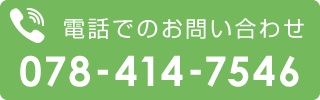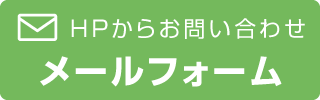相続登記に関するご相談が増えてきたので、手続きの流れを簡単にお話しておこうと思います。
相続登記を司法書士に依頼するタイミングは様々です。
・被相続人が亡くなってすぐ。
・市役所や区役所で死亡に伴う手続きをした時に司法書士が必要だと知った。
・金融機関での口座凍結解消手続きをした後に不動産の手続きも必要なことを知った。
・相続財産が多かったため、税理士に依頼していたが、その税理士から紹介を受けた。
などが多いパターンかと思います。
まず、一つ目のパターンであれば、司法書士が戸籍の収集から登記申請まで全てを行うことになります。
そのため、このパターンを中心にお話をしていこうと思います。
1、依頼
相続登記を司法書士に依頼する場合、司法書士から以下のような情報提示を求められます。
・被相続人の持っていた不動産の所在地等(正確に分からない場合は、どの市区町村にあるか)
・被相続人の最終住所・最終本籍地
・相続人の概略(正確に分からなくとも大丈夫です。)
・遺言書の有無
・遺産分割協議の有無(これから行う場合は見通し)
以上の情報があれば、司法書士は登記に必要な書類を収集することができます。
この時、固定資産税の評価証明書若しくは納税通知書を提示すれば相続登記の見積もりも素早く算出してくれるはずです。
司法書士に以上の情報を提供し、費用面・手続きの説明に納得できれば委任契約を締結します。
最初から司法書士に依頼する場合、以降は司法書士から送られてくる書類に署名押印するだけです。
2、書類の収集(司法書士側の動き)
依頼時に集めた情報から司法書士は必要な書類を収集します。
戸籍謄本関係を市区町村の市民課へ請求。
不動産の所在が不明であれば、資産税課と法務局へ。
等々、各役所へ請求を行い、書類を収集していきます。
3、署名・押印書類の作成(司法書士側の動き)
収集した書類並びに依頼時に聞き取った内容をもとに登記に必要な押印書類を作成していきます。
具体的には、遺産分割協議書・登記委任状・上申書(登記が複雑な場合)等を作成します。
作成した書類は各相続人へ送付されます。
当事務所であればレターパックも同封しておりますので、署名と押印が終われば、印鑑証明書と共に返送していただくだけです。
4、登記申請(司法書士側の動き)
返送していただいた書類を最終確認し、管轄の法務局へ申請を行います。
5、権利証(登記識別情報通知)の返却
登記が終われば(1週間~10日ほど)法務局から司法書士へ新たな権利証が送付されます。
現在は登記識別情報通知という名前になっています。
司法書士は新たな権利証を受け取ると、登記簿謄本の交付申請を行い、登記簿上で間違いがないかを確認し、依頼者へ送付します。
6、入金
当事務所では、基本的に後払いで費用をいただいております。
新たな権利証を送付する際に請求書を同封しておりますので、それに従い、入金していただきます。
入金確認後、領収書を発送し、手続き終了となります。
以上が相続登記の流れです。
もし、金融機関での手続きの後に私たち司法書士へ依頼する場合は、金融機関への手続きで使用した戸籍等は再利用できます。
したがって、依頼時に戸籍関係をお預かりし、手続きに着手することになります。
当事務所では、様々な状況での相続登記を受任しております。
明治以降登記がなされていない土地であったり、相続人が他の国籍、相続人が外国にいる等々。
中々ネットで調べても分からないという方是非当事務所へご連絡ください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。