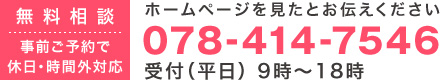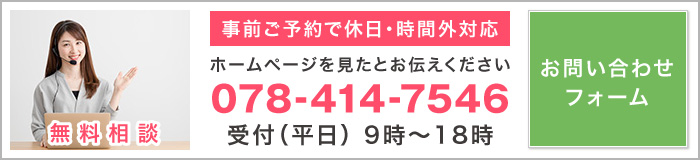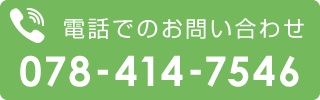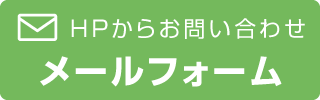遺言の方法としてよく用いられるのは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
本来、遺言とは、遺言書の全文を遺言者自身が自書する「自筆証書遺言」という形式が原則であったはずです。
しかし、現在は多くの場合、「公正証書遺言」が用いられるようになっています。
その理由はいくつかありますが、まず、様式面での縛りが大きいことが挙げられます。自筆証書遺言に関する民法の条文は第968条です。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
(3 加除変更方法について)省略
ちなみに、この第968条2項が今回の改正により新設された部分です。以前はこの条文がなかったため、相続財産が多岐にわたる場合であっても全ての財産を自書する必要があったのです。
つまり、相続財産が多岐に渡る方はこの時点で自筆証書遺言による遺言方法を敬遠していたのです。
しかし、今回の改正により、相続財産のリストをワープロ等で作成することが可能となりました。これは自筆証書遺言を遺言の選択肢とする上で大きな改正と言えるでしょう。
少し話は変わりますが、公正証書遺言による場合、公証人に支払う手数料は相続財産の額によって決まります。つまり、相続財産が多岐に渡る方が公正証書遺言により遺言を作成した場合は、手続き費用が高額になってしまう可能性が高いのです。
今回の改正により、自筆証書により遺言書を作成した場合は当然ですが費用はかかりません。
また、自筆証書遺言によった場合、問題となるのは、様式面だけではなく、保管方法やその後の検認といったものもあります。
しかし、この部分についても今回の改正により、「法務局での遺言書保管制度」がこの令和2年7月より開始されます。この制度を使えばこれらの問題も解消されます。
つまり、今回説明しました様式上の緩和と合わせると、公正証書遺言と同じような効果をより簡単に、廉価に行うことができる可能性があります。
当事務所では、従来の「公正証書遺言」はもちろん、今回改正のあった最新の方法での「自筆証書遺言」もサポートしています。
自分にはどの方法があっているのか、お問い合わせだけでも結構です。是非お声掛けください。
このコラムを通して、少しでも皆さまの抱えるお悩みの解決の糸口が見つかれば幸いです。
神戸市中央区に事務所を構える私たち小鴨司法書士事務所は、「身近な街の法律家」として、特に個人のお客様の相続手続き(遺産整理・相続登記)や、生活再建に欠かせない債務整理(借金問題)の解決に力を注いでいます。
法律家への相談は敷居が高いと感じるかもしれませんが、当事務所はご依頼のほとんどが個人のお客様であり、誰もがアクセスしやすい事務所づくりを徹底しています。ご相談の際は、必ず司法書士である私が丁寧に聞き取りを行い、明瞭な料金体系で安心して手続きを進めていただけます。
相続、借金、将来の不安…。どんなお悩みも、まずは当事務所にお話しください。あなたの「最初の一歩」を全力でサポートいたします。
面談の結果、ご依頼に至らなかった場合も費用は一切いただいておりません。どうぞお気軽に無料相談をご活用ください。